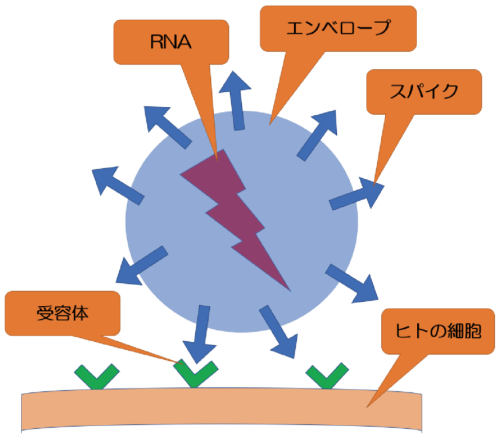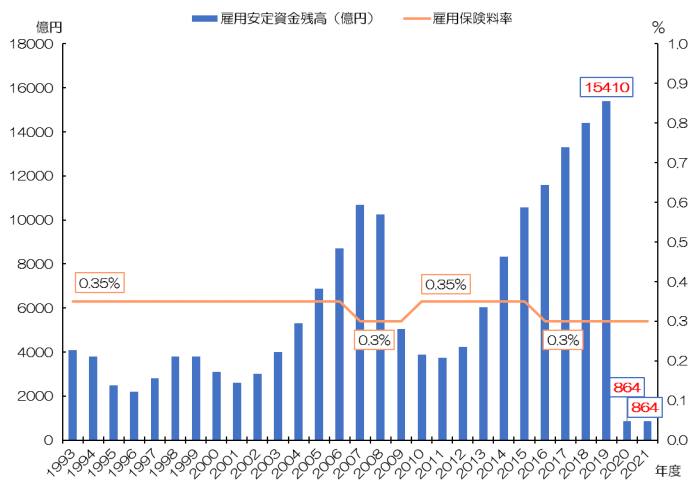新型ウイルスが母子世帯を直撃
=子ども7人に1人が貧困状態=
新型コロナウイルスの感染拡大とともに、元々経済的に厳しい立場に置かれていた人々が、一層苦しい生活を余儀なくされた。中でも、大きな声を上げることができない貧困家庭では、子どもや親の不安が拡大する一方だ。
新型ウイルスの感染が発覚する前の2019年秋、東京都文京区の成澤廣修(なりさわ・ひろのぶ)区長から、貧困家庭の子ども支援に関するお話をうかがう機会があった。その中で、成澤区長が力説していたのが、「こども宅食」という行政サービス。経済的に厳しい家庭に対し、2カ月に1回食品を届ける取り組みである。
このサービスは2017年にスタート。当初の届け先は150世帯だったが、2019年秋には約580世帯まで拡大した。成澤区長は「食品を届けることが目的ではない。お届けするプロセスの中で、その家庭と(区が)信頼関係を築き、必要な支援に繋げていくことが目的であり、子どもたちの未来を創っていきたい」という。
「こども宅食」配達準備中のスタッフ
(提供)文京区(こども宅食コンソーシアム)
最近、新型ウイルスの影響を成澤区長にメールで尋ねたところ、おこめ券やQUOカードなどを届ける「こども宅食:緊急支援」(約600世帯)を始めたという。やるべき事は山ほどあるはずなのに、弱者への配慮を忘れない迅速な対応に頭が下がった。
文京区に限らず、全国の自治体が子どもの貧困対策に取り組む。いや、取り組まざるを得ない状況にある。「平成28年国民生活基礎調査」(厚生労働省)によると、2015年の子どもの貧困率(=年間可処分所得122万円未満世帯の子どもの比率)は13.9%に上り、子どもの7人に1人が貧困状態にある。
なぜ122万円で線引きするのか。実は貧困の定義には相対的貧困と絶対的貧困の2つがある。先進国では前者が指標になり、国民所得の中央値(=可処分所得の低い順に並べた時の真ん中の値)の半分に届かない世帯が貧困ということになる。なお、絶対的貧困については、世界銀行が「1日当たり1.9ドル以下の収入で生活している人」と定義する。
先の調査によると、相対的貧困を示す線引きは1997年の149万円から、2015年までに27万円も低下した。日本人全体が貧しくなっているといえそうだ。また、独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査結果によると、2018年の母子世帯の貧困率は51.4%に達し、実に半数以上が貧困状態にあるのだ。
このように子育てに苦悩する貧困世帯に対しても、新型ウイルスは容赦なく襲い掛かった。シングルマザーを支援するNPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」の調査結果からは、母子世帯からの悲痛な叫び声が聞こえてくる。
「電気代、食費などの支出が大幅に増え、この先生活が不安です。家賃も払えないほど困窮しています」「収入が減り、新学期に新しく買うものも我慢してもらって買ったりできない」
その上で、母子世帯は「迅速な現金給付」「子どもが安心していける場所」「就学援助を受けている家庭への給食費返還」「休業補償」などの実施を切望している。
一方、政府は曲折の末、2020年度第1次補正予算で全国民一律10万円の現金給付や児童手当の1万円上乗せを決定した。まだまだ不十分との声もあるが、まずは一刻も早く各家庭に届けなくてはならない。
行政の支援は当然として、わたしたち一人ひとりにできることはないのか。成澤区長は、「ふるさと納税で貧困対策に参加してみては」と提案する。また、子どもの貧困問題に取り組むNPOのホームページには、寄付やボランティの募集が掲載されている。中には「ソーシャルウェンズデー」と題し、水曜日を社会活動に充てるよう呼び掛けるところもある。
新型ウイルスとの戦いは長期化が必至。わたしたちの生活も、ウイズコロナを前提にしなくてはならない。それに合わせ、子どもの貧困問題に取り組む必要がある。貧困世帯の子どもが元気でなければ、社会から活力が失われ、明るい未来も開かれない。セーフティーネットが不十分な社会なら、だれがリスクを取りイノベーションを生み出すだろうか。情けは人の為ならず。決して他人事ではない。
タグから似た記事を探す
記事タイトルとURLをコピーしました!
大塚 哲雄